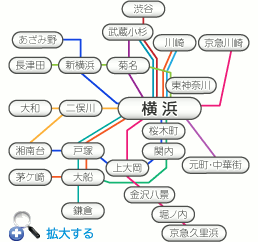業務上堕胎致死傷罪とは、医師・助産師・薬剤師・医薬品販売業者が、妊娠中の女子の嘱託を受け、または妊娠中の女子の承諾を得て堕胎させ、よって女子を死亡させ・傷害を負わせた場合に成立する犯罪です。
業務上堕胎致死傷罪は、刑法214条後段に規定されています。
業務上堕胎致死傷罪の刑事罰は、6月以上7年以下の懲役です。
業務上堕胎致死傷罪は、業務上堕胎罪を犯した上で女子を死亡または傷害を負わせる犯罪ということになります。
このように、基本的な犯罪を犯したことで、重い結果が生じた場合に、基本的な犯罪よりも加重された刑罰を科す犯罪を結果的加重犯といいます。
業務上堕胎罪を犯した者が、女子を死亡させることや傷害を負わせることの意思を有していた場合は、殺人罪または傷害罪が業務上堕胎罪とは別に成立することになり、業務上堕胎致死傷罪は成立しません。
ですから、業務上堕胎罪を犯した者が、女子を死亡・傷害させる意思がないことが本罪成立のために必要ということになります。
業務上堕胎致死傷罪に関し、基本的な犯罪である業務上堕胎罪に関する部分については、業務上堕胎罪を参照してください。
また、死亡は、一般的な見解によれば、①自発呼吸の停止・②脈(心拍)の停止・③瞳孔反射機能の停止という3点から心臓の死を判定し、これを人の死とされます。
傷害とは、人の生理機能の障害とされています。
判例上、病気を感染させること、キスマークをつけることも、傷害として認められています。
この点、堕胎の場合、どうしても一定程度母体に対して傷を負わせることが想定されますので、堕胎行為に伴って通常発生する程度の傷の場合には、本罪の傷害にはならず、業務上堕胎罪の範囲で処罰されるものと思われます。
堕胎そのものは失敗して未遂にとどまったものの、母体について死亡または傷害の結果が発生した場合に、業務上堕胎致死傷罪が成立するかについて、学説上の争いがあります。
この点、堕胎そのものが未遂の場合は、本罪は成立しないとする有力説があります。
この有力説は、業務上堕胎罪について未遂犯が処罰されないことから、堕胎が未遂の場合は、本罪も成立すべきでないとします。
この説だと、堕胎が未遂で、母体に死亡または傷害の結果が発生した場合は、過失致死罪または過失傷害罪だけが成立することになります。
本罪の成立を認める説は、堕胎行為は、母体の生命・身体に対して危険のあるものであり、堕胎が失敗しても、本罪の成立を認めるべきとします。
本罪は、妊娠していた女子を死亡・傷害させた場合に成立する犯罪であり、堕胎行為の結果、生きて産まれた赤子を死亡・傷害させても、本罪にはなりません。
最高裁判決昭和63年1月19日は、医師が妊娠26週の胎児の堕胎を行い、推定体重1kgの未熟児を保育器等の整った病院の医療を受けさせれば、生育する可能性があることを認識し、かつ、そのような措置をとることができたにもかかわらず、放置したため、出生の約54時間後に未熟児が死亡した事案について、業務上堕胎罪と保護責任者遺棄致死罪の成立を認めました。