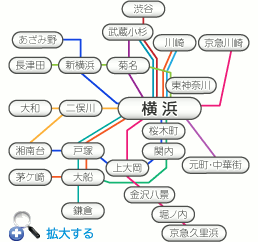同時傷害の特例とは、2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、またはその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共犯でない場合でも、共犯と同様に取り扱うことです。
同時傷害の特例は、刑法207条に規定されています。
同時傷害の特例が想定しているのは、いわゆる同時犯というものです。
同時犯とは、2人以上の人が、同一の機会に、それぞれ独立して同じ犯罪を実行することです。
例えば、Aさんが遠くを歩いているBさんに怪我をさせようとして、石を投げつけたところ、Aさんとは無関係にCさんがBさんに向かって石を投げつけた場合に、2人は同時犯になります。
そして、刑法207条の同時傷害の特例は、上記事例で、Bさんに石が当たってBさんが傷害を負ったが、AさんとCさんのどちらが投げた石が当たったのか不明だった場合に、AさんとCさん両方に傷害罪の成立を認めるのです。
AさんとCさん両方に傷害罪の成立を認めることは、AさんとCさんが共犯だったのと同様に取り扱うことになります。
ちなみに、同時傷害の特例がなければ、どちらの投げた石によってBさんが傷害を負ったか不明である以上、誰にも傷害罪が成立しません。Aさんも、Cさんも、Bさんに向かって石を投げたことで、暴行罪が成立すると思われます。
Cさんがどちらかの投げた石で傷害を負っている場合に、どちらの石かの立証は困難な場合が多く、そのような場合に傷害罪が成立しないことは、不合理と考えられたのだと思われます。
ですが、同時傷害の特例は、「疑わしきは被告人の利益に」という原則に反し、疑わしきは被告人の不利益となる嫌疑刑を是認するもので、憲法違反であるとの学説もあります。
そして、多くの学説は、同時傷害の特例が憲法違反とまでは言わないものの、同時傷害の特例について消極的に考えています。
同時傷害の特例は、暴行を加えた者のうち、傷害を負わせた者が不明である場合、または傷害の軽重が不明である場合に認められます。
したがって、暴行を加えた者が、自分の行為で傷害が発生したわけではないことを立証した場合には、同時傷害の特例は適用されず、暴行罪しか成立しないことになります。
つまり、本来、暴行行為と傷害結果の因果関係の立証が必要なところ、同時傷害の特例の存在により、逆に暴行行為と傷害結果の因果関係が無いことの立証を要求されることになります。
このようなものを挙証責任の転換といいます。
判例は、暴行の結果、被害者が傷害を負っただけでなく死亡してしまった場合、つまり傷害致死罪が問題となる場合でも、同時傷害の特例の適用を認めます(最高裁判決昭和26年9月20日)。
この点、立証が困難なのは傷害致死罪でも同様として判例に賛成する学説もありますが、多数の見解は判例に反対しているものと思われます。