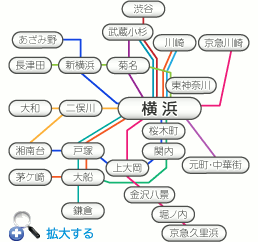傷害致死罪とは、身体を傷害し、よって人を死亡させた者に成立する犯罪です。
傷害致死罪は、刑法205条で規定されています。
傷害致死罪の刑事罰は、3年以上の有期懲役(20年以下)です。
傷害致死罪は、傷害罪を犯した上で、被害者が死亡した場合に認められる犯罪です。
殺人罪は、殺意(殺人の故意)がある場合に成立するのに対し、傷害致死罪は、殺意まではなく傷害の故意がある場合に成立します。
傷害致死罪のように、行為者が認識していた結果より重い結果が生じた場合に、より重い刑罰が科せられる犯罪を結果的加重犯といいます。
傷害致死罪は、結果的加重犯の典型です。
傷害致死罪は、殺人の故意は不要ですが、結果として被害者がが死亡したことについて、過失(死亡結果の予見可能性)が必要かどうかについて、学説上の議論があります。
多数説は、死亡の結果について予見することが不可能な場合には、責任主義(行為者を非難し得る場合でなければ刑罰を科さないという原則)の見地から、傷害致死罪の成立を認めるべきでないとし、過失または予見可能性の存在を要件とします。
これに対し、判例は、死亡の結果についての過失や予見可能性を不要とします(大審院判決大正14年12月23日。最高裁判決昭和26年9月20日)。
このように、学説の多数と判例は対立しているようにみえますが、実際には、傷害致死罪が成立するような事案において、行為者が死亡の結果について過失や予見可能性がないということは非常に稀なはずであり、それほど大きな差はないと思われます。
また、傷害致死罪は、傷害の故意がある場合だけでなく、暴行の故意しかない場合でも成立すると考えられています。
例えば、大きな石を被害者に向かって投げるも、被害者に命中させずに脅す意思の場合には、暴行の故意しか認められませんが、結果として石が被害者の頭に命中して死亡させた場合にも、傷害致死罪が成立します。
死亡の結果は、行為者の傷害行為との間に、相当因果関係(原因と結果の関係)があることが必要と考えられています。
これに関連して、傷害行為の相手方とは別の者が死亡した場合に、傷害致死罪が成立するか問題になった裁判例があります。
東京地裁判決昭和49年11月7日の事案は、高速道路で前方を走行する自動車に嫌がらせの目的で幅寄せをしたところ、ハンドル操作を誤ったことで前方の自動車に追突してしまい、その前方の自動車を対向車線に押し出すことになり、反対車線を走行してきた自動車と衝突したことで、その反対車線の自動車の運転手が死亡したというものです。
同判決は、この事案で、傷害致死罪の成立を認めています。
ただし、似たような事案で、飲食店内で、手拳で顔面を殴った上で突き飛ばしたところ、突き飛ばされた者が別の者が衝突し、その別の者が肋骨骨折となり死亡してしまったという大坂高裁判決昭和38年1月28日があります。
同判決は、死亡した者に対する暴行行為がないとして、傷害致死罪の成立を認めませんでした。
このように、下級審判決は、結論を異にしており、決着はついていないと思われます。